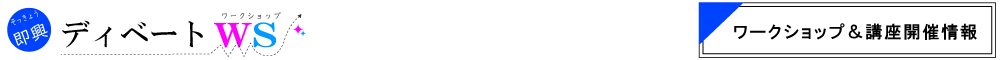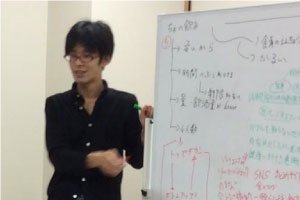ディベート向きの人と不向きな人の違い
このブロックでは、ディベートを学ぶとどんな技術が身につきますか?という質問に答えていきます。
是非とも即興ディベートワークショップに参加をするかどうかの判断材料にしてください。
ディベートで学べること
- 「聴く」→「考える」→「まとめる」→「伝える」を一連の動作
- 自身の考えや思い込みの囚われず第三者の立場で物事を考える
- 咄嗟(とっさ)の切り返しや問題や課題を分析して指摘する力
など、私たちが日常で誰かとコミュニケーションをするさいに必ず生じる相手との意見や考えの食い違いなどに対応する技術を身につけることができます。もちろん、ノウハウを教えて終わりではなく、キチンと実践に落とし込む実践トレーニングもございます。
世の中には、優れたセミナーや講座はたくさんありますが、ディベートがひとつ抜き出ているとすれば、それは競技形式で参加をする空間にあります。これまで即興ディベートワークショップ参加者様の中で寝た方は誰もいませんでした。ちょっとした自慢です。(笑)
良くも悪くもそんな強烈な特徴があるディベートなので、お勧めな人とそうでない人についてご説明します。
もちろん、現時点では、ディベートのスキルや経験は問いません。
こんな方にはディベートに向いている
- 意見と人格を分けることができる
- 【本当】に自分で考える意志がある
- 意見や考えをため込まない。何らかの形で伝える方法を模索中
1の意見と人格を切り分けることができる、に関しては、誰が言ったか?ではなく何を言ったか?で物事を考えられる人ですね。世の中は、何を言うかではなく誰が言うかの世界ですが、ディベートは逆なんです。
- 何を言うか?
- どのように伝えるか?
- どんな理由を示すか?
の世界です。
例えば、ある労使問題をテーマにディベートの試合をするとします。あなたが企業の人事部長さんでも、社労士さんでも、その地位や権威を理由に自分の意見を正当化することはできません。
例:私の意見を採用するべきです。なぜなら、私は社労士だからです。
この場合、社労士だから何が言えるの?と突っ込まれるだけです。地位や肩書ではなく、それを使って限られた時間内にどんなことが伝えられるのか?なのです。
もちろん、役職や肩書を前面に出すことが完全にNGなわけではありません。そこから何をどのように伝えられるか?が大事にです。
それなので、たとえ年下の方でも相手が誰かではなく、何を述べたかに対して耳を傾けられる人ならディベートには向いています。もちろん、間違っていると判断したらドンドンと突っ込んで構いません。ディベートにおける反論とは、相手を尊重している証のようなものなので。
2.の本当に自分で考える意志がある、は、言葉のままです。
ディベートの試合は、究極的には正解が存在しません。最近だと、子供たちに答えがない「考える授業」をさせたい!というお考えをお持ちの方がいますが、本当に答えがない問題って結構ツライ、のが正直なところです。
これを知っている人は意外とディベートに向いています。
こんな方はディベートが不向きかも
- セミナージプシーの方
- ノウハウコレクター/教わり中毒の方
- 自分で判断をするのが嫌いな方
あと、「日本人の文化にディベートは合わないだろ」と決めつけている方。正直、ディベートには向いていません。
この手のタイプの方は、物事をスグに一般化して決め込んいる傾向があるため、相手から反論を受けたときに柔軟に対応ができなくなるケースが多いからです。多面的に物事を考えるよりも、自我のほうが強いんですね。
逆に、あらゆることに完璧や正解は存在しないから、物事を細かく検証してみよう!と考えることに意義をお持ちの方はディベートに向いています。ディベートでは、自分と違う意見に対してどのように対処するかが求められるからです。
どんな人が即興ディベートワークショップに参加をするの?
- 自分の意見や考えを堂々と人前で伝えられるようになりたい
- 質問や反論を受けても咄嗟(とっさ)に切り返せるようになりたい
- 相手が納得するような質問や反論ができるようになりたい
- 自分の考えを論理的にまとめて伝えられるようになりたい
業種・職種問わずエンジニアや会計・労務などの分野で専門職/コンサルタントの方からのお申し込みを頂きます。女性で多いのが教育関連のお仕事に就いていたり、自身で何らかの事業にを行っている方からお申込を頂きます。
現時点でのディベートの経験・スキルは問いません。また、日常で議論をする機会の有無も不要です。完全初心者・未経験者に向けた形でディベートを教えております。
逆にこのような方はディベートには向いていません